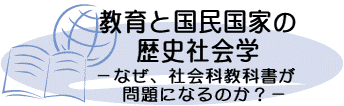
(初出:早稲田大学社会学院生研究会公式ウェブサイト、1997年8月)
ここ数年、中学・高校で使われている社会科の教科書(とりわけ歴史教科書)の記述内容をめぐる論争が、その熱を増しています。教科書に書かれる内容は、専門家がしっかりと調べた事実を載せていれば問題はないように思えるのに、なぜ論争の的になるのでしょうか? このページでは、この問題を歴史社会学の立場から、「教科書とは私たちにとってどのような存在なのか」に焦点を当てて考えたいと思います。はじめに現在の論争を簡単に振り返ったあと、日本の代表的な教科書として山川出版社の『世界史』を所々で引用しながら(この教科書は、内容が最も詳しく、かつ学校での採用率が抜きんでていて、代表執筆者の入れ替わりがほとんどありません)、話を進めていくことにします。
●90年代の歴史教科書論争
1995年に東京大学教授の藤岡信勝さんを中心に組織された「自由主義史観研究会」は、産経新聞社を初めとする新聞・雑誌数社の後押しもあって多くの文化人に呼びかけ、歴史教育の現状への問題提起を盛り上げています。保守系言論人の方々によるこの教科書見直しの動きの基本主張を一言で表現するなら、「“戦後平和主義者”たちの過剰な自責感情・贖罪感・自虐史観」を批判する、ということになるでしょう(久保紘之「天下不穏」『産経新聞』1996年8月26日夕刊1面)。この主張を基礎として同会は今、明治期日本の「元気」を称揚し、極東裁判を批判し、「南京事件」「従軍慰安婦制度」を見直しています。その動きが代議士の勉強会とも相互に補完し合って、ナショナリスティックな政治的主張を増幅してもいます。しかしそのプロテストがあまりに広範囲に展開された結果、本来教育学者であるはずの人が歴史学の専門家と喧嘩をしたり、政治家が自らの信念にもとづいて新聞記者を啓蒙しようとしたりといったような、やや錯綜した様相もこの議論については見受けられるのです。
その一方、朝日新聞社が上の動きと正面から対立する記事を、やはり新聞・雑誌を通して多数取り扱うなど、左派系勢力による巻き返しも盛んです。元東京教育大学教授の家永三郎さんが提訴したいわゆる「教科書裁判」の最終判決が1997年8月29日に下されたこともあって、1950年代末以来文部省の教科書行政に異を唱え続けていた人々の活動も賑々しくなっています。教科書検定訴訟を支援しているグループの刊行物の中では、産経新聞社らによる異見提示の動きを「第3次教科書偏向キャンペーン」と称するようにもなりました。
現在行われている歴史教科書論争は、直接的には中学校用歴史教科書に「従軍慰安婦」の記述を掲載することの是非が焦点となっています。しかしこの論争は、第二次世界大戦終結以後半世紀に亘って議論され続けている、初等・中等教育用歴史教科書のあり方をめぐる論争(それは小学校社会科、中学校社会科歴史分野、高校日本史、高校世界史に及んでいます)の延長線上にあるものと考えることができるのです。
●国家にとっての歴史教育の役割
そもそもなぜ、教科書に書かれていることが、このように激しい政治的な対立の焦点となるのでしょう? 歴史教科書の内容など、歴史学者がしっかり調べて事実を載せていれば問題はないようにも思えます。それなのに教科書をめぐって対立が生じる根本的な理由は、そもそも私たちがその中で生きている国家が存続するために、教科書が極めて重要な役割を果たしているからなのです。
私たちが今その中で暮らしている「国家」の存在を、社会学では「ひとつの制度にすぎないもの」と考えて、「さまざまな人種や民族の人々が、お互いに同じ国民であるという意識を共有することでなりたっている国家」という意味で、「国民国家」(nation
state)と呼びます。この制度は、私たちがイメージするよりもずっと「新しい制度」です。国民国家は、世界史的には18世紀から19世紀にかけて、産業革命・市民革命を契機に、西ヨーロッパ地域から世界に広がっていきました。この動きによって、それまでの宗教的な共同体が、新たな国境の概念によって細かく分割されていったのです。日本の場合、この契機は明治維新と考えることができます。
【地理】
国民国家は、この「お互いに同じ国民である」という意識を世代を越えて、地域を越えて国民の間に伝達するための様々な手段を必要とします。学校組織というのは、実はそういった役割を最もよく果たしている制度のひとつであるのです。私たちは地理の授業で世界地図を見ますが、そこでは「日本」が中央に位置し、赤く塗られています。朝鮮半島や樺太や台湾との間の海には、常に黒い太い点線で国境が示されています。小学校入学以来教えられてきたこれらの知識を通して、私たちは「自分は日本に住んでいる」という感覚を持つようになります。
【大河ドラマ】
さらにまた、自分たちのネーション(国家・国民)を想像する感覚は、時間を遡って過去にも投げかけられています。例えば、私たちはNHKの大河ドラマの中で、織田信長と豊臣秀吉が、徳川家康と伊達政宗が相互に言葉を交わすのを特に違和感もなく観ています。それはその劇の中で、彼らが時代がかった共通語を話しているからです。しかし歴史考証をどこまでも厳密に行えば、彼らは育った階級・地域によって違う言葉を話し、直接的なコミュニケーションには相応の困難さが伴ったはずです。では、彼らにスムーズな意志疎通を行わせているの誰なのでしょうか? それは私たち後代の日本人です。私たちが彼らを日本人の祖として位置づけるが故に、彼らは標準的な時代劇言語で話すよう演出されるのです。
【日本史】
私たちがこのように歴史を捉える意識を持つにいたったのもまた、教科目としての「歴史」を私たちが学校で習ったからなのです。「日本のあけぼの」から始まって「大和朝廷」に繋がっていく歴史の語り方自体が、極めて人工的なものでもあります。そしてそのような教育が一般民衆レベルで行われるようになったのが、明治維新以後、新たに始動した国民国家の中で制定された『学制』以降のことです。この時「国史」という概念が作られ、日本の歴史が語られ始めたのです。
歴史教科書の内容が、時として「国家存立の要」とまで表現されて厳しく検討される背景には、私たちが採用している国民国家のこのような性質があるわけです。私たちが学ぶ「歴史」には、常に「現在」の私たちの都合が入り込んでいます。さて、ではこの件に関して、私たちが学んできた戦後の日本における歴史教育の内容とそれを取り巻く状況はどうであったのでしょうか? それは本当に「自虐的」なものだったのでしょうか? 国民国家の本質とかけ離れたものであったのでしょうか?
●戦後日本の「歴史」の歴史
戦後の日本では、まず1945年の敗戦から1952年4月まで、GHQ主導で新しい教育制度が整備されました。この時期の教育行政では、極端なナショナリズムや高度に中央集権化された教育制度を廃止することが目標とされ、教材の選択においても現場の自由が幅広く認められる方向が示されていました。いわゆる「戦後民主主義」教育ですが、そこで流通していた教科書知識には、第二次世界大戦の戦勝国全体を「祖国と民主主義の防衛のために戦うという民主主義国家」と称し、敗戦国を「全体主義の悪」「狂暴な軍国主義」といった表現で形容し、戦争責任はすべて軍部に押しつけてしまう部分が多くありました。これを、日本というネーションにとって自虐的なものと言うことは可能でしょう。それ自体が、戦勝国のイデオロギーであったからです。
しかし1951年のサンフランシスコ講和条約の締結と冷戦の開始によって、50年代半ば以降にこの種の教科書知識は急速に姿を消すことになりました。1955年には、政権党であった民主党によって「うれうべき教科書の問題」キャンペーンが展開され(第1次教科書偏向キャンペーン)、それまで模範的教科書とされていた小学校用社会科教科書『あかるい社会』などが左翼的であるとして批判されるようになったのです。レッド・パージを押し進めるアメリカの政策によっても、新生日本のこの傾向は許容されたのでした。教科書の中では、「戦勝国」イコール「民主主義国家」である、とは言われなくなります。ソビエト連邦を民主主義国家と呼べなくなったからです。
さらに60年安保の闘争を経て右派・左派双方においてそれぞれの文脈での「自国への愛着」が強調されるようになると、「国および国民の自主的な立場を正しく身につけることが出来るような教科書」(『教育委員会月報』1964年5月)が国民的に求められるようになりました。その結果、1966年に中央教育審議会が発表した『期待される人間像』という答申の中には、「第二次世界大戦における敗北は、日本の国家と社会のあり方および日本人の思考法に重大な変革をもたらした。特に敗戦の悲惨な事実は、過去の日本および日本人のあり方がことごとく誤ったものであったかのような錯覚を起こさせ、日本の歴史および日本人の国民性を無視する結果を招いた」という一節が明記され、これに基づいて同時期の文部省による教科書検定では「太平洋戦争は大東亜戦争と書きなおせ」「戦争の反省は子どもには不必要だ。削れ」「日本の教科書だから中国侵略と書くな」といった意見が付されるようになったのです。
このように、「戦後民主主義」は国民国家というシステムを尊重する思想としての「国民国家主義」(nation-state-ism)によって克服されているわけです。ポツダム宣言という条約を受け入れて降伏したのだから第二次世界大戦の終結は無条件降伏ではない、とする検定意見は1960年代に多く出されましたが、これは明らかに国家の主権の継続性を尊重する思想に基づいています。また戦時中に強制連行された朝鮮人たちを「当時は日本人であった」とし、「国民徴用令に基づいた徴用であるから強制連行ではない」とする検定意見も、「国民」概念に則ったものです。
そしてそのような「国民国家主義」はすぐに、自己の属するネーションを他から区別して意識し、その統一・独立・発展を志向するナショナリズムへとオフィシャルに整備されていきます(official
nationalism)。日露戦勝によって「アジア諸国に大きな刺激を与え」「欧米列強の支配下にあった諸民族を刺激し」た、あるいは「戦時中に日本軍が欧米勢力を東南アジアから追放したこと」がアジアの独立を促した、とする自民族中心主義に基づく教科書知識は、60年代から70年代にかけて登場してくるのです。また同時期には、「中国」という呼称を中華思想に基づくものであるとし、それに組みしないところで歴史を語るために、「中国」を「シナ」へと全面的に改称したりもしました。
というように、1950年代半ばまでを「日本ナショナリズムの崩壊期」と呼ぶことは可能でしょう。しかし戦後の日本はサンフランシスコ講和によって独立した国民国家に返り咲いたのであり、国民国家となった以上、そこで執り行われる教育には上記のようなナショナリズムが入り込んでいたわけです(1956年の白書における「もはや“戦後”は終わった」という宣言は、この点で誠に的を射ていたことになります)。先にも述べましたように、国民国家とは「国民」が「自国」を想像することによって維持・存続するシステムであり、「国家」の想像の仕方を「国民」に強要するシステムをその機能の一環として本来的に含んでいるものなのです。歴史教科書知識は「国民」が「国家」を想像するためのマテリアルに他ならず、それゆえに「国家主義」(ナショナリズム)に基づく傾向は不可避です。戦後の日本においてもその原則は貫かれているのであり、その意味から戦後の歴史教育は決して「自虐的」なものではなかったのだと、言うことが出来るのです。
●国家の枠組みを越えた動き(トランスナショナリズム)と歴史教科書知識の変質
では冒頭に述べた保守系勢力の人々が現在批判している対象というのは、本当は何なのでしょうか? それは1980年代半ばから90年代にかけて生じてきた、従来の国民国家の原則と微妙にズレを見せ始めた歴史教育の動向です。この現象は、産経新聞が言うような戦後教育の特色というよりは、むしろ20世紀末のネーション(国家・国民)それ自体の「グローバリゼーション」の一環として考えてみることができるのです。
「グローバリゼーション」とは、人間の様々な活動が地球規模に広がっていくことです。このことを現代イギリスの社会学者アンソニー・ギデンズは、大量輸送の手段や地球的なコミュニケーションを瞬時に可能にする手段が発達することによって生じてきた「遠隔的行為」を基礎とする「時間と空間の再編成」、というような言い方で定義します。すなわち、私たちは自分自身や自分の周りにいる人のふるまい、それから自分を取り巻く環境を常に見つめながら(モニタリングしながら)自分の行動を決定し、行動することによって周りに影響を与えているわけですが、そのように自分や周囲を見つめ・それに影響を与える手段が発展することにより、物理的により遠く離れている対象とも関係を取り結ぶことが出来るようになった、ということです。
日本の教育においてその傾向が生じ始めたのは70年代です。その頃から日本の社会科学においては、ヴェトナム戦争の社会的影響もあって、アメリカが掲げる「世界の見方」を改めて考え直す動きが出始めます。また家永三郎を原告とした一連の教科書訴訟が起こされることによって教科書検定制度の実態が公開されるようにもなりました。一方国外では東南アジアでの反日暴動が生じるなど、いわゆる「片面講和」の代償が現れ始めました。グローバリゼーションの世界的傾向は、国民国家間の相互監視を次第に強固なものとする風潮を促しており、その結果日本の戦後ナショナリズムは国際的に(国家間で)検証されることになったのです。
すなわち、歴史教科書知識の中には「現在」の日本を取り巻く環境の変化がよりビビッドに反映せざるを得なくなったわけです。その好例が、朝鮮半島への「進出/侵略」問題でしょう。70年代までの歴史教科書においては、戦前の朝鮮半島への日本の勢力拡大がどのような経緯を経て行われたのかについては、情報はほとんど与えられていませんでした。しかし日本と韓国が関係を密にしていく過程と調和する形で、80年代に入ると韓国併合についての情報量が加速度的に増加するようになります。「現在」の日韓関係が密接になるほどに、「過去」の日韓関係も詳細に語られるようになったのです。そのような傾向の中で増えた情報の中に、「大陸への進出」という言葉が含まれていたのでした。「進出」という語に対する中国・韓国からのクレームは、82年に出るべくして出たのだといえます。というのも、それまではクレームの対象となる記述さえ存在していなかったのですから。
この国際的抗議は「進出」という語を「侵略」へと変える力をもっていましたし、また国内では「侵略」という言葉で15年戦争のイメージを形成した国民たちが、15年戦争についての閣僚の発言を1986年から相次いで問題であるとするようになりました(それ以前ではその手の発言が「問題」にさえならなかったことに注意)。80年代の自民党を支えた新保守主義は教育の国家管理を再度強めようとしましたが(第2次教科書偏向キャンペーン)、国家間・諸個人間のグローバルなモニタリングに基づく歴史意識は、国家がオフィシャルに定める歴史意識とはズレを見せるようになったのです。
もちろんそのようなモニタリングの一つひとつは、基本的にはナショナルな性質を帯びていたと言えます。しかしナショナルなもの同士がぶつかり合うことで結果として、「何処のネーションに属する者が歴史を語ってもこのようになるのではないか」と思われる種類のジェネラルな「歴史を描写する意識」が創発してきたのです。90年代にも引き続いているこの傾向の中では、ある種無国籍的な、すなわちトランスナショナルな(国家の枠組みを越えた)歴史が語られており、その記述は「戦後民主主義」期の「自虐的な」ものとは完全に異なっているのです。この傾向の中で詳細に語られるようになったのは「南京事件」や「皇民化政策」の記述だけではなくて、「原爆投下」や「シベリア抑留」に関しても同様だという点が非常に重要です。
日本の歴史教育の面でみられるこのような動きは、実は政治・経済の面で生じているボーダーレス化の動きと関係があります。ボーダー(国境)を厳密に考えると、物理的・地理的国境、政治的国境、経済的国境、文化的国境が想定されますが、前3者は現在かなり乗り越えられつつあるのです。航空機・船舶・情報通信の技術の進歩によって、まず物理的・地理的国境が人間の行動の障碍となる度合を格段に弱めたのがこの20年間です。そしてその技術躍進を背景にして、政治・経済の諸問題も一国の内部で考えていられるものは少なくなりました。89年の中国の天安門事件、91年のソ連からのバルト3国の独立劇などから分かるように、ある政治的問題の当事者が巧みに世界と交信することによって、その問題を一国の国内問題に止めない傾向が強まっています。経済については、金融市場の世界規模化、自由貿易への不可逆な動きなどを見れば、もはや語る必要もありません。これらが政治・経済の面でのトランスナショナルな動きです。かつての「インターナショナル」はまず国家があり、それらが交差・交通することによって成立していましたが(いわゆる多国籍的な状態)、「トランスナショナル」は国家の区別なしにそれらを再編します(無国籍的な状態)。資本主義の成熟とテクノロジー(特に輸送・通信手段)の進展にともない、既存の国民国家の枠組みは次第に無化されてきているのです。
教育などにあらわれる文化的国境は、それに比べると未だ根強く残っているわけですが、これも政治・経済の流れと相補的に変化していく可能性は大いにあります。なぜなら、そもそも現在私たちが歴史教育や地理教育を通して内面化してきた日本のイメージ自体も、かつて19世紀後半に当時の輸送・通信手段の技術レベルや国家の政治状況・経済状況との関わりの中で作られてきたものであるからです。しかし20世紀も末となった現在、私たちを取り巻く環境は、今ある国民国家が成立した時点のそれとは大きく変化しているのです。個人にとって利用可能な輸送・通信手段の多様化・高速化・細分化は、個人が世界に対して抱く認識の幅と深さを既存のネーションの枠組みの内部に限定させない力をもっています。現在、私たちは個々人で情報を入手し、個々人でその情報を管理・運用し、自らの世界像を作っていける可能性を広げています(現にあなたがWWWを通してこのページを目にしているように)。それは時に、《場の感覚》の希薄な最も原始的な狩猟社会に比せられるものです。情報の狩猟者や採集者もまた、縄張りにこだわりません。80年代半ばから日本の歴史教育に現れ始めた新しい歴史記述の意識は、そのような手段を用いる人々の相互作用の中で形成されてきたものとして、国境を乗り越える作用と絡めて性格づけされるべきです。そこでは、どこのネーションに属する者が歴史を語っても同意を得られるようなジェネラルな歴史記述が模索され始めているのです(それゆえ、冒頭で紹介した保守系勢力の人々による歴史教育の見直しは、そのような根無し草の風潮に対抗する、自分自身の出自への帰属性を構築する動きと位置づけることができます)。
社会学的な視点から戦後の歴史教科書のうつり変わりを考えていくと、昨今の教科書知識の変化は以上のように捉えられます。今後、教育制度の中での歴史の語り方がどのような性質をより強く帯びていくのかは、日本という国民国家がシステムとして変質することをどの程度容認することができるかという問題です。私たちはこの問題を、このページで採用したような社会学的な視点からも考えていかなくてはならないのです。
《「教科書と国民国家の関係」を考えるためのお薦め文献》
岡本智周『国民史の変貌――日米歴史教科書とグローバル時代のナショナリズム』日本評論社、2001
藤岡信勝『近現代史教育の改革』明治図書、1996
高嶋伸欣『教科書はこう書き直された!』講談社、1994
B・アンダーソン『増補版 想像の共同体』白石隆・白石さや訳、NTT出版、1997
E・ホブズボーム『創られた伝統』前川啓治他訳、紀伊国屋書店、1992
村上泰亮『反古典の政治経済学 上・下』中央公論社、1992
大前研一他『「国家」の限界が見えてきた。』ダイヤモンド社、1997
トップページへ戻る
|